「建築を褒める力」 宮沢洋氏の講演を聞いて
2025.06.17 更新 カテゴリ:コラム
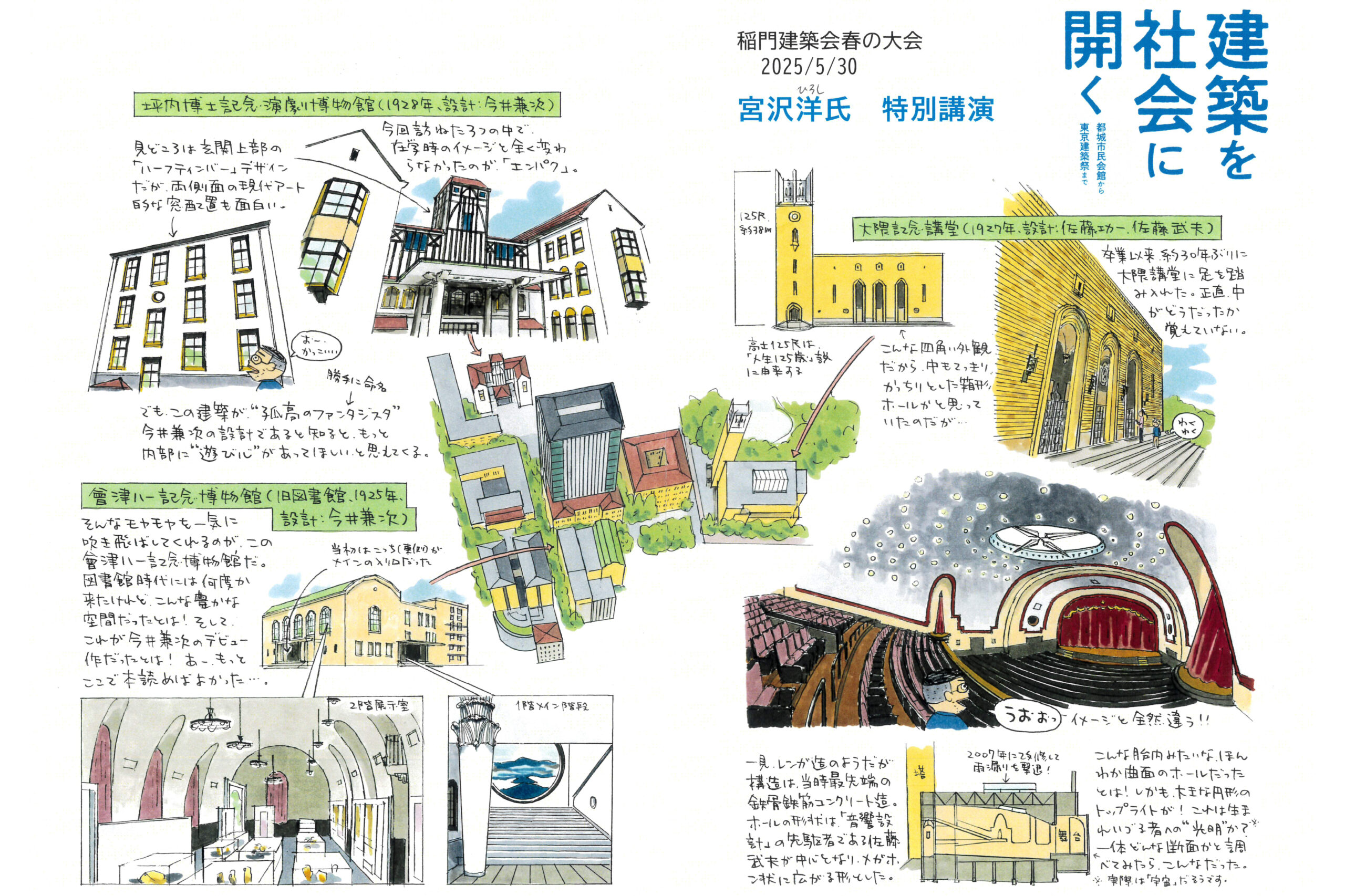
『昭和モダン建築巡礼』などのイラストで知られる「画文家」宮沢洋氏の講演会を聴いた。
会場は早稲田大学理工学部キャンパス。
稲門建築会春大会のイベントの一環で、なじみ深い場所だ。
似顔絵道場で培ったデッサン力と旺盛な行動力で、磯達雄氏と共に全国の名建築を巡る宮沢氏。
建築を一般の人にも「わかりやすく、楽しく伝える」ことを信条に、20年にわたり建築巡礼を続けてきたという。
私も『日経アーキテクチュア』連載の熱心な読者の一人だ。
講演で印象に残ったのは、巡礼初期に訪れた都城市民会館でのエピソード。
あの名建築について、館長が「新しい施設ができるので2年後に解体します」と平然と語ったという。
雨漏りや使い勝手の悪さばかりが話題にされ、菊竹清訓による建築の文化的価値は完全に見過ごされていた。
「戦後のモダン建築は、気づけばいつの間にか消えていく。
戦前の様式建築は残っても、モダニズム建築は理解されない」その危機感が、
建築を“褒めて伝える”活動の原点となったという。
そして自ら『菊竹清訓 建築巡礼』(現在は絶版)を制作するほどの熱意には、深く共感を覚えた。
都城市民会館はその後、保存運動が巻き起こり、議論を呼んだものの、残念ながら解体された。
「残る建築と消える建築。その違いは何か?」
宮沢氏の答えは明快だ。
「技術ではなく、感情。美しい建築など、愛される建築が残る」と。
つまり、建築が好きな人を増やすことが、保存の鍵なのだ。
JIA再生部会では、個々の建築の保存要望を訴える活動よりも、
建築を使い続けるための制度的障壁を見直す“川上のアプローチ”を大切にしてきた。
例えるなら「子どものサッカー」のようにボールに群がるのではなく、
「大人のサッカー」のように、フィールド全体を見渡して動く
──そんな姿勢で、建築基準法や都市計画法の課題を調査し、発信してきた。
だが、これからはそれだけでは足りないのかもしれない。
宮沢氏のように、建築の魅力をストレートに伝え、ファンを増やす。
感性に訴え、共感を広げる。そうした“前線でのプレー”も、今後ますます重要になるだろう。
特に、モダニズム建築の価値は、有名建築家の名前だけでは測れない。
その空間が生み出す力、その時代の社会的背景を含めた物語性があってこそ、真の価値が立ち上がる。
サッカーの戦術が日々進化するように、私たちの活動スタイルも進化が求められている。
情報発信が重要性を増すいま、建築の魅力を“褒めて伝える”力を、あらためて見直したい。
(ポスター文・画:宮沢洋、本文:柳沢伸也)
※早稲田キャンパスのポスター転載は宮沢洋氏より許諾済みです